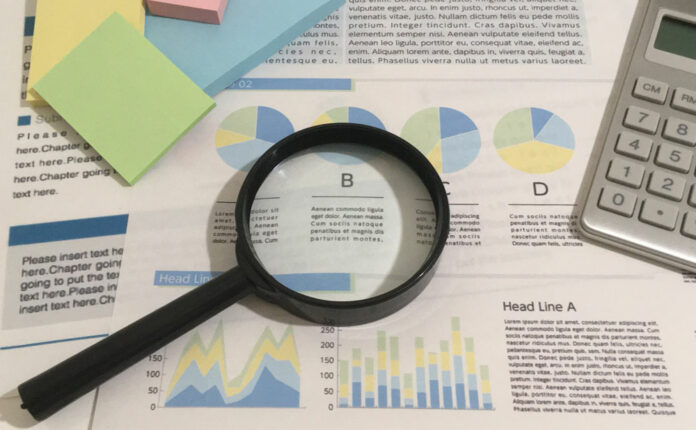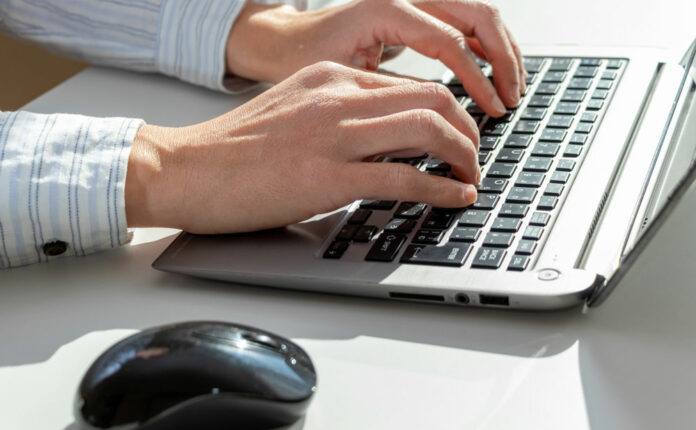インターネットやデジタルサービスが日常生活において欠かせない存在である今、私たちは多くの場面で個人情報を提供しながらサービスを利用しています。
そして、それらのサービスを利用することは便利である一方、提供した個人情報の取り扱いについては不安を抱く方も少なくありません。
そのため、プライバシーポリシー(個人情報保護方針)は利用者の不安を軽減し、安心してサービスを利用してもらうために大きな役目を果たしています。
本コラムでは、プライバシーポリシーとは何なのか、策定する場合どのような内容を盛り込むべきかなど、法律の観点も交えながらわかりやすく解説します。
プライバシーポリシーとは

プライバシーポリシー(個人情報保護方針)とは、企業や団体など事業者が、自身が運営するウェブサイトやサービスにおいて、利用者から取得する個人情報(氏名やメールアドレス、住所や勤務先など、個人を特定できる情報)の取り扱いについて説明した文書です。
主に、その取得方法や利用目的、管理方法などについて明示します。
これは、個人情報の保護とその適正な利用を目的して制定された個人情報保護法において、事業者がユーザーから個人情報を取得する場合、同法で定める事項についてユーザーに対し公表することが義務付けられているためです。
これはプライバシーポリシーの策定自体を直接的に義務付けるものではありませんが、多くの事業者は自身が所有するウェブサイトやサービスの入力フォームで個人情報の取得するため、必然的にそうした場所にプライバシーポリシーを掲載する必要性が生じます。
プライバシーポリシーに掲載すべき主な内容

個人情報保護法の観点からも、プライバシーポリシーには最低限、以下のような内容を盛り込む必要があります。
- 利用目的
取得した個人情報をどのような目的で使うのかを具体的に記載します。たとえば、「サービス提供や品質向上のため」「お問い合わせ対応のため」「新商品案内など広告配信のため」などが一般的です。 - 第三者提供について
個人情報を外部の企業や団体と共有する場合、その事実と目的、共有先や共有範囲などを含め記載する必要があります。また、第三者提供を行わない場合は「第三者提供は行いません」と明確に記載することが望ましいとされています。 - 安全管理措置
取得した個人情報を安全に保管するための取り組み(暗号化、アクセス制限など物理的な仕組みや社内研修など)を説明します。 - 開示・訂正・削除の手続き
利用者が自分の情報の開示や訂正、削除を求めたい場合の方法や連絡先を記載します。 - お問い合わせ先
個人情報に関する問い合わせ窓口を明示することも大切です。会社名、住所、担当者名、メールアドレスなどが一般的です。
作成時の注意点と個人情報保護法の観点

プライバシーポリシーを作成する際には、次のような点に注意が必要です。
まず、曖昧な表現を避けることが重要です。特に利用目的についてはできるだけ具体的に特定することが望ましく、例えば、事業活動のためなどといった抽象的な表現ではなく、メールアドレスの情報を取得するであれば「メルマガを送るため」などと利用目的を明確にするよう心がけましょう。
次に、ポリシーは「建前」ではなく、実際の業務フローや管理方法を正しく反映していなければ意味がありません。つまり実態に合ったものである必要があります。万が一ポリシーと実態に乖離がある場合、後からそれが発覚すると大きな問題になることがあるため、常に確認するようにしましょう。
また、法改正への対応も重要です。個人情報保護法はこれまで時代に合わせて改正が繰り返されており、2022年の改正では、個人情報の漏えい、滅失、毀損など本人の権利や利益を害する恐れが大きい場合の報告が義務化されました。プライバシーポリシーの内容そうしたタイミングで見直しを行う必要があります。
最後に、利用者がアクセスしやすい場所に掲載することも重要です。例えば、ウェブサイトのフッターなどに「プライバシーポリシー」へのリンクを設置し、どのページからでも閲覧できるようにすると良いでしょう。
まとめ
プライバシーポリシーは、利用者との信頼関係構築や、トラブルを未然に防ぎ、法律を遵守するために欠かせない文書です。個人情報を適切に取り扱っていることを示すことは、事業者やサービスの信頼性を高めるうえでも大きな意味を持ちます。
形式的なものではなく、実態に即して、誰にでも分かる言葉で丁寧に作成することが大切です。