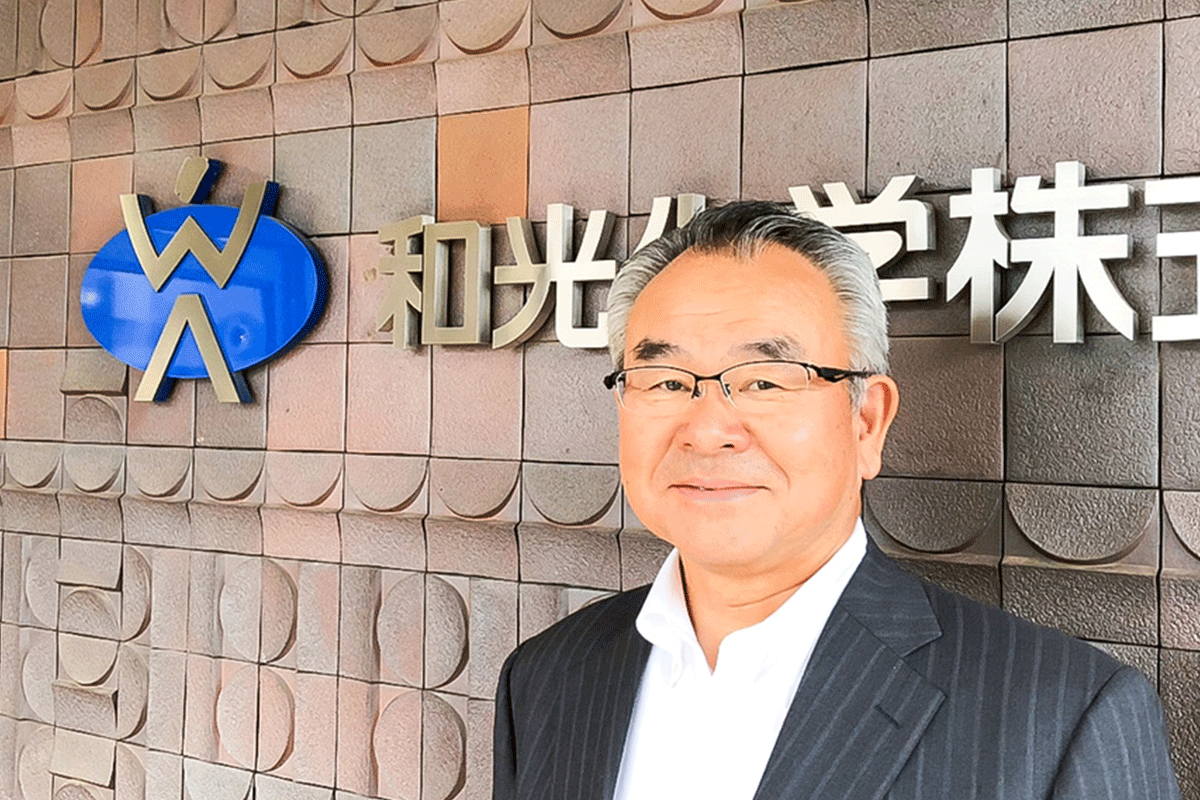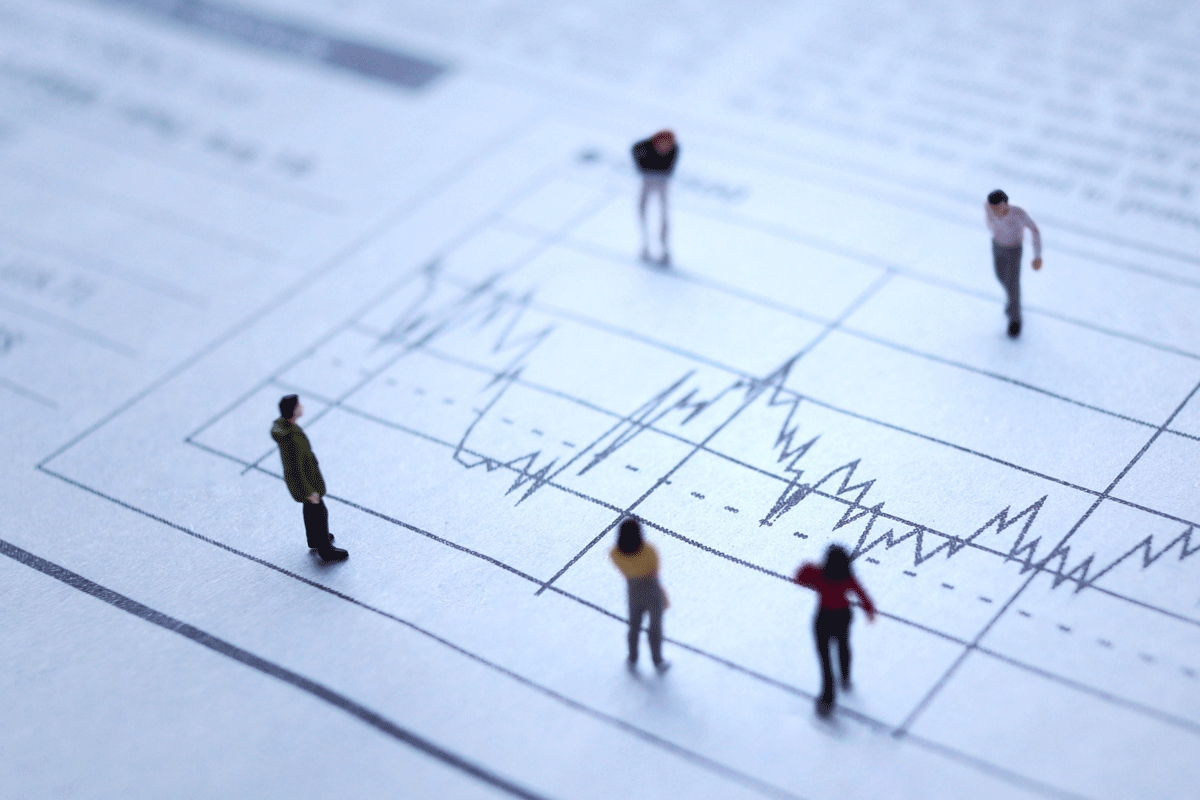日本では一つの商習慣である名刺交換。
営業における打ち合わせをはじめ、イベントや展示会など、日々さまざまな場面で交換される名刺には、会社名や氏名、部署や役職、連絡先など重要な情報が記載されています。
一般的に、年間で平均200枚から300枚の名刺を交換するとされるビジネスマンにおいて、名刺を紙のまま保管していては管理が煩雑になり、せっかくの人脈情報も必要な時にすぐに確認できないといったことが起こります。そこで近年、多くの企業や個人の間で利用されているのが名刺管理アプリです。
そして、この名刺管理アプリの中核を担う技術がOCR(光学文字認識:Optical Character Recognition)です。
本コラムでは、OCRとはどのような技術か、また名刺管理アプリにおいてどのように活用されているのか解説します。

OCRとは何か?
OCRとは、画像データに含まれる文字を読み取り、テキストデータに変換する技術です。例えば、紙の印刷物や、スマートフォンなどで撮影した写真の中にある文字情報を読み取り、編集可能なテキストデータに変換することができます。
OCRの技術は、新聞や書籍の電子化、行政文書のデジタルアーカイブ化、さらにはレシートや領収書の読み取りによる会計処理の効率化など、様々な場面で活用されています。特に日本語に対応したOCRの進化により、縦書きや複雑なレイアウトの文章でも高い認識精度が実現されつつあります。

名刺管理におけるOCRの役割
名刺管理アプリにおいて、OCRは極めて重要な役割を果たします。
ユーザーがスマートフォンのカメラや専用のスキャナーなどで名刺をスキャンすると、画像はOCRによる解析を経て文字認識され、会社名、氏名、部署、役職、住所、電話番号、メールアドレスといった項目に自動で分類されます。
この自動認識により、スピーディかつ効率的に名刺情報がデータ化されます。また、データ化された情報はクラウド上に保管されるため、PCやスマートフォンなどから閲覧や検索が可能になります。
さらに、近年の名刺管理アプリではOCR技術に加えてAI(人工知能)や大規模言語モデル(LLM)も併用され、複数の名刺から会社の所在地やドメインなどの共通情報を補完したり、誤認識の修正提案を行ったりする機能も登場しています。
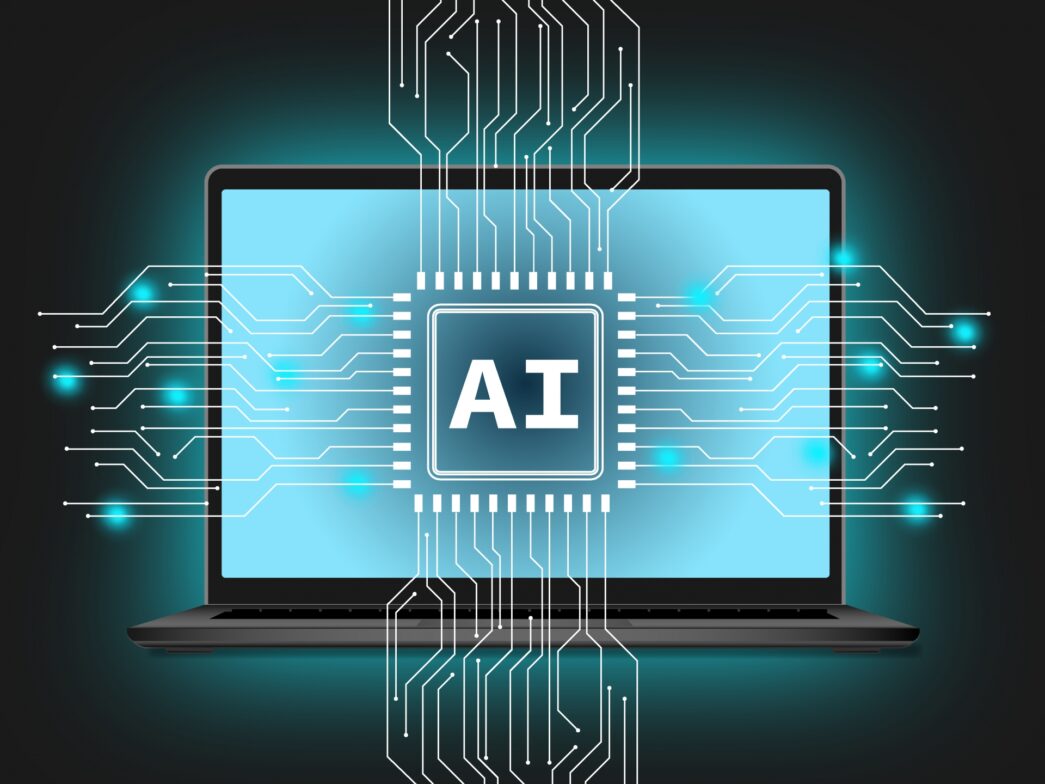
認識精度はどれくらい?
OCRの認識精度はソフトよって異なります。
参考までに、法人向けの名刺管理アプリであるネクスタ・メイシはOCRと前述のAIやLLMといった技術を併用することで現在約95%の認識精度を実現していますが、残念ながら100%ではありません。
なお、OCRは性能に関わらず、一般的には以下のような条件下では高い精度が出やすい傾向にあるとされています。
- 印刷が鮮明でフォントが標準的なもの
- スマートフォン撮影時の手ぶれがない
- 名刺のレイアウトがシンプルである
一方で、以下のような場合には誤認識が発生する可能性があります。
- 複数の団体や企業名、部署名などが併記されており主となる所属先が判別しにくい
- 装飾的なフォントやロゴと文字の境界が曖昧な場合
- 縦書きやアルファベットと日本語が混在する構成
そのため、多くの名刺管理アプリでは、OCRによってデータ化された後、人の目によるチェック(オペレーター確認)というハイブリッドな仕組みを採用しており、結果99.9%の正確性を実現しているサービスもあります。

OCRの今後と名刺管理の展望
OCR技術は今後も進化を続け、AIとの組み合わせによってさらなる高精度化・自動化が期待されています。また、OCRの活用は名刺管理アプリ以外でも進んでおり、請求書や契約書など、さまざまなビジネス文書のデータ化において活用されています。
これまでアナログで行ってきた名刺管理作業も、OCRによってデータ化することで大きく変わりつつあります。そして、名刺のデータ化は管理の効率化のみならず、ビジネスの様々な場面でのデータ活用を可能にしてくれます。
OCR技術を搭載した名刺管理アプリを導入することで属人的であった人脈情報が可視化され、名刺を企業の資産として最大限に活用することが可能になります。